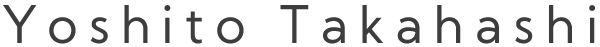Texts List
絶対視感(日本語)
光山 清子
高橋淑人が作家として現代美術界に足を踏み入れたのは、1979年東京の真和画廊での発表であり、それは1982年頃から日本にも上陸したニューペインティング旋風が吹き荒れる直前のことであった。また、日本の圧倒的な経済力と欧米思潮におけるポストモダニズムの台頭を背景として、80年代にはそれ以前の時代には見られなかったような強い関心が欧米の美術関係者から日本の現代美術に寄せられるようになったが、そこで焦点があてられたのは、テクノロジーを謳歌する都市的感性に根ざし、日本と西欧を問わず様々なイメージを日本のプレモダン美学の一つの特徴である折衷を介在として結合する斬新な表現であった。
1990年代に入り、日本のバブル経済の崩壊を経て既成の価値観が崩壊してゆく中で、より若い世代のアーティスト達は、西欧の文化的・美術的価値観に裏打ちされたいわゆる「ハイ・カルチュア」あるいは「ハイ・アート」を転覆させることをもくろんだ。日本における西欧近代との葛藤を照準に入れて、それまで周辺に追いやられていた戦後日本のアニメやマンガなどのサブカルチュアの表現領域を取り込みつつ、日本の社会に鋭く切り込むような批評性をイメージに託したのであった。このような1980年代から90年代にかけての日本のとりわけ絵画における目だった動向に対して、いわゆるイメージの描写とは異なる地平で絵画に取り組んできた高橋は、常に一歩を隔ててきたといえよう。では、その間、この作家は何をどのようなかたちで探求してきたのであろうか。
作家の本質を考える時に最も重要なことのひとつとして、何がその作家を創作に駆り立てているかということがある。かつて高橋はいわゆる美術における「絶対音感」にあたるものについて言及したことがあった。(1) これを敢えて「絶対視感」と呼んでみよう。視覚芸術に携わる上で、学習や訓練では会得しようのないある感覚を指している。これが満たされることへの渇望が、すなわち彼の創作活動の源であり、作品の基準を決定するものでもあり、また作家としての在り方を方向づけているものと言って過言ではないであろう。試行錯誤を経て、変化を重ねて、めざすものを創りあげるというよりは、この「絶対視感」を羅針盤として、直感的に何かを探りあてようとする。論理を積み重ね、弁証法論的に世界を構築する態度とは異なるアプローチである。
そのようにして高橋がまず制作の中で探求するのは、彼が日常的に体験する様々な感情を昇華することである。そのプロセスで豊かに異なる色彩、明暗、構成をもった創造物が立ち現れてくる。それら作品を通して、観る者の個人的経験に根ざす感情や、人類が共通にもつ生命体としての記憶を呼び起こそうとするのである。そこで新たに、彼が呼ぶところの「未だ視ぬものへの記憶」が創出されることもまた願いながら。(2)
このように彼は美術との関わりにおいて、極めて個人的な在り方を選択してきた。彼にとっての美術は社会との直接的コミュニケーションの手段ではない。これは、美術作品の社会性が求められ、ジャーナリスティックな内容が好まれる近年の傾向の中で、現代社会における美術の役割を改めて考えさせる事柄であろう。また、自分自身の中に存する「絶対的なもの」を信じる彼の人間としての在り方は、情報化が世界規模で著しく進行し、価値の相対化が行われていくポストモダン的社会現象の中で、またそれに素早く反応していく今日のアート・シーンにおいて、現象の彼方にある人間存在の深みへと導く「遠いまなざし」(3)を示唆している。
高橋の「絶対視感」とはある程度まで生まれもって備わったものともとれるが、そのように解釈するよりは、むしろ彼が育った環境の特徴を指摘したい。高橋の生家は、彼の祖父が明治時代に創業したという、中国、日本、朝鮮半島のものを専門とする古美術商を営んでいる。そのような家に生まれ、高価で稀有な数々の名品が、まるで彼にとってはおもちゃのように常に身近に存在していたそうである。とりわけ、白磁と青磁への深い愛着が育てられ、それらの物質感や抽象的な形態の成り立ち方に大きく影響されたという。(4) 高橋が絵画を語るとき、その視感だけでなく、触感に言及するのも、このあたりに起因するのであろう。
しかし、高橋の自己形成はまさに戦後日本のアメリカ文化の覇権下で成されたことも見逃せない。14歳から16歳頃にかけてドイツ表現主義の絵画に心酔した彼は、その後次々と紹介されるアメリカを中心としたアートの動きに興味をもったという。また、大学時代には、欧米的近代思考を批判したモノ派の仕事を知り、多くの同世代の作家と同様に強い刺激を受けた。一方でその頃アメリカ抽象表現主義にも深く魅せられたのであった。(5)
そうした模索の時期を経て、1977年、23歳の時に初めてヨーロッパを訪ね、その地が生みだした古今の美術品を目にした時に、当時はまだエア・ブラッシュとフォトグラフを用いてアメリカのスーパー・リアリズムを「模倣」していたという高橋は、自らが美術家として立つ基盤は西欧の土壌のものではないことを直感したと告白している。(6) 彼がそこで近代日本に移入されたものとしての「美術」の問題を認知したことは確かであるが、単に東と西の異なる文化の溝を埋めようという目的をもったというよりも、むしろ東と西という違いを超えた人間存在の本質に触れる仕事を志したと解釈するのが適切であろう。このような姿勢はその後の高橋の創造活動に一貫してみられるものである。
自らの拠って立つところに自覚的であった高橋が、1980年代半ばに作家としての評価を得たのは、和紙と版の使用による独自な表現であった。それは、コンクリートで作られた版の上にアクリル絵具をのせ、そこに和紙をおき裏から滲ませる。また同時に和紙の表からも絵具をのせ、滲み込ませる。絵画の支持体である和紙は、同時に裏と表の出会いの場となる。(7) これは、カンヴァスに油彩で描くという西欧の伝統的な絵画の成り立ち方とは明らかに異なるものである。このように高橋の仕事は絵画そのものの構造を探求してゆくものとして評価を得てきた。(8)
ジョセフ・ラヴは、この版の使用を、高橋が自らの創作物にある距離をおいていることとして指摘し、陶芸家が素材とダイアローグを行いながら制作することとの類似性を指摘しているが、(9) これは高橋のやきものの成り立ち方に対する愛着と一致する。
作家自身は、版を用いて裏からも彩色するという技法を用いることについて、和紙という素材と創り手としての彼自身の意志を共存させるためであると言明している。(10) このような感性は、彼の東洋的な自然観に根ざすものであろう。自然と対時するのではなく、自然と共存すること。自然界が矛盾するものがせめぎあうことによって、様々な要素を排除することなく共存させるようなバランスの上に成り立っているように、高橋の作品にも多くの相反する要素が重なり合い、せめぎあいながら、ある調和を生み出そうとする。高橋によれば、それら相反するものは感情であるという。喜び、悲しみ、憎しみなど彼が人生の中で体験する感情であり、全ての人間がもつ経験である。それらが渾然一体となった状態は、すなわち人間の精神であり、魂である。高橋淑人はそれを絵画で表現したいのである。(11)
日本美術における美的伝統を、自然との関わり合いの中で自己を思索しミニマルな表現をする傾向と、それとは異なり人工的なものを愛でキッチュな表現を好む傾向に大別すれば、高橋が紛れもなく前者に属する作家であることに異存はないであろう。自己の感性における自然からの影響を自ら認める高橋だが、それは単なる自然への回帰志向や制作の上で素材に拘泥するようなこととは一線を画し、あくまでも人間の精神性を探求する上でのことなのである。(12)
1995年以降、高橋は版を使用しなくなる。その理由として作家自身は、版を使用せずとも技法上同じ効果が得られるようになったことと、作品の大きさが版のサイズに規定されずに済む利点を挙げている。(13) しかし、それ以上のことがこの技法上の変化から読み取れるのではないか。
まず、版を使って制作されていた作品を、いわゆる西欧的な意味での「ペインティング」と呼ぶには抵抗がある。なぜなら、「ペインティング」とは基本的に「塗る」ことを意味するからである。(14) 高橋の場合は裏からも彩色する訳であるから、伝統的な絵画の材料であるカンヴァスと油絵具を用いないことはともかくも、これは伝統的な意味での絵画とは言い難い。そうであるからこそ、絵画そのものの構造を探求する仕事として当時評価されたのである。しかし、版を使わなくなった現在、相変わらず和紙とアクリル絵具を用いてはいるが、その制作方法は基本的には伝統的絵画の原型から逸脱するものではない。矩形の支持体の表面に絵具を塗り重ねているのである。すなわち、高橋の出生は基本的に「ペインター」といえよう。版を床に水平に置いて制作をしていた時も、アクション・ペインティングとは異なり、「描く」という感触であったと述べていることは興味深い。(15)
版を使用しなくなってから、和紙の生成りがかいま見えることもなくなり、絵具はより厚塗りとなってきている。その結果、絵画の表面は物質感を増し、東洋美術の豊かな環境の中で育まれた高橋の絶対視感は、この作家をして「やきものでいえば、白磁や青磁のような作品を創りたい」(16)とまで言わしめているが、まさにその地平に向かっていることを想起させる。何も表面に見えないようでいて、その下に幾つもの層が、その層の間の空間が、そしてその空間をよぎる光、その光のもうひとつの姿である闇が織りなしている世界である。今や素材と自分の意志との共存を考える必要もなくなったところに高橋は降り立ったのではないか。それらはまるで自然においては異なる要素がせめぎあって調和するように存在している。
このように、彼の仕事は絵画を表面として、物質として成り立たせることによって、絵画ならではの空間と光、そして闇の表現を追及するものであるが、同時にそこに奥深い精神的世界を創出させる場でもある。そのような場においての他者との交感を彼は試みているとも言える。現代の情報が氾濫するポストモダン的社会で、このような場を求めている人は少なくないであろう。
以上のような高橋の作家としての生い立ちとその仕事の軌跡を辿る時、彼が日本的モダニズムの文脈における一つの好例であり、その可能性を示唆していることに気づく。自己の感性に忠実であったところから、伝統的な西欧の絵画構造とは異なる方法論を試みた後、再び絵画の基本に達し、しかも彼が絶対視感と呼ぶところの東洋的あるいは日本的感性を拠りどころとして矛盾するところなく、力強い創作活動を展開しているのである。単なる「オリエンタル」志向、いわゆる浅薄なジャポニスム的なものに陥ることなく、作品は彼の個人性の徹底的な表現となっており、それ故に普遍的なクオリティを獲得していることは、言葉で十分に証明できることではないにしろ、作品を観れば自明のことであろう。
ここで詳述するまでもなく、明治期に西欧美術の概念が輸入されて以来、日本の作家たちはいかにこれを自身のものとして消化するか、あるいはこれに拮抗する彼ら自身のパラダイムを打ち立てるかで葛藤してきた。冒頭で述べた1990年代の日本のアート・シーンの前景に現れた若手作家の仕事が、いわばその苦闘を横目にみながら、この本質的な問題を軽やかにまたぎ越すかたちで挑戦したとするならば、高橋を含む一連の作家たちはまたぎ越さずに、その厚い壁を通り抜けようとしている。高橋はその挑戦を、徹底的に個人的になること、すなわち自己を追求すること、自らの絶対視感を頼りにすることで遂行してきた。
高橋の「絶対視感」は、別の言い方をすれば、いわば「伝統」という言葉で置換することも可能である。日本現代美術と伝統の関係は、日本的モダニズムにおける種々の問題を理解する上でその鍵を握る領域でありながら、その検証は充分には行われてこなかったといえよう。このような研究が進められることは、高橋のような日本の創り手達を理解する上で重要である。非西欧の土壌から生まれてくる美術については、ポストモダニズムの論考で論じられるものの、未だ確固とした方法論があるとは言えない。これら作家一人一人の仕事を考察することによって、その道も開かれてゆくであろう。
脚註
- 高橋に彼の作品と日本あるいは東洋の文化的伝統の関係を尋ねた際、次のように述べている。「墨絵ややきものに影響を受けた。特にやきものの表面とその存在感や物質感。その存在感というものは、ヴィジュアルに感じるだけではなく体で感じるようなもの。また、墨絵とは、例えば、牡丹というものを比喩として、そこに精神性をストレートに託していき、それ以外のものはない。これは西欧的空間をもつ絵とは異なる。僕の美術に対する入り方、いわは絵に対するいわゆる絶対音感がそこでできてしまったと思う。基準がそこにできてしまった。やきものの肌も牡丹の花も一緒で、創る人間としての表現のとらえ方や託し方はそこにあると思う。」また、次のようにも述べている。「いわゆる現代美術と呼ばれているものも、何千年の美術の流れの中で見たい。その中に絶対音感というものがあると信じたい。僕がもつ絶対音感は東洋的絶対音感の部分だと思う。アフリカにはアフリカで生まれた絶対音感があり、西欧で生まれたら西欧に生まれた絶対音感があると思う。」
高橋との筆者のインタヴュー( 2001年4月20日 ) - 高橋淑人「未だ視ぬものへの記憶」[アーティスト・ステイトメント] ( 未発表、1999年 )
- 次の著書から引用した。押田成人『遠いまなざし』( 地湧社、1983年 )
- 註2前掲文
- この自己形成期については、註2前掲文及び筆者とのインタヴュー( 2002年10月29日 )を参考にした。
- 高橋淑人「Untitled」[英文アーティスト・ステイトメント] ( 未発表、1984年 )
また、西欧現代美術が圧倒的優位を占めた当時の美術界にあって、高橋に東洋美術の在り方を追求することの自信を与えた人物として、郭仁植が挙げられる。高橋淑人「郭先生を想い」『郭仁植〈追悼文集一偲ぶ〉』( 郭仁植を偲ぶ会編/ギャラリーQ発行、1989年 )pp.29-30 - 横山勝彦氏はこの時期の高橋の仕事の意味を技法の観点から鋭く分析し、評価している。横山勝彦「高橋淑人( Reviews )」『美術手帖』第620号(1990年2月号) pp.211-212
- 例えば、三田晴夫氏は、1993年高橋の東京画廊での個展に際して「絵画発生の原理を探る姿勢」と評価している。三田晴夫「ダイナミックな画面」毎日新聞1993年3月12日(夕刊 )
- ジョセフ・ラヴ「The World of Wind: Pictures of Yoshito Takahashi」[未掲載オリジナル英文テキストから翻訳した日本文テキスト]『Yoshito Takahashi Exhibit』( 旧Laboratory/現Gallery Miyashita、1985年)[ページ記載なし]
- 高橋淑人「あるがままにあること—もう一度平面へ」[アーティスト・ステイトメント]『北海道現代作家展』(北海道立近代美術館、1986年) p.17
これは次の展覧会カタログにも再録されている。『NEW TRENDS: 世田谷の新世代』( 世田谷美術館、1987年 ) pp,18-19 - 註2前掲文
- 高橋と筆者とのインタヴュー( 2001年4月20日 )
- 高橋と筆者とのインタヴュー( 2002年10月29日 )
- 高橋の画家としての特質を考える上で、特に次の論文を参考にした。中林和雄「絵画について」『現代美術への視点:絵画、唯一なるもの』( 東京国立近代美術館、1995年 ) pp.11-17
- 高橋と筆者とのインタヴュー( 1999年6月28日 )
- 高橋と筆者とのインタヴュー( 2001年4月20日 )